大白法 平成26年9月1日刊(第892号)より転載

法華経について⑪
『化城喩品第七』の後半 前回は、法華経迹門のうち、正宗分の広開三顕一における三周の説法中、第二の譬説周の授記段に当たる『授記品第六』の四大声聞の授記について述べました。
続いて、未だ開三顕一の法門を領解できない下根の声聞に対して説かれた因縁説周の正説段に当たる『化城喩品第七』の前半部分についても学びました。
そこでは主に大通覆講を説かれて、釈尊在世の弟子は、遥か昔の三千塵点劫において釈尊から下種結縁され、今日に至る因縁があることを明かされています。この大通覆講について、簡単におさらいすると、大通とは、三千塵点劫の昔に出現して法華経を説いた大通智勝仏を言い、覆講とは、大通智勝仏が説いた法華経を再び十六王子が講説し、大衆に結縁したことを言います。
その十六番目の王子が釈尊であり、この時の釈尊の説法を聴聞して、後に退転してしまった人々は、三千塵点劫もの間、三界六道という苦しみの世界に沈淪します。釈尊は、この間、垂迹の仏として長い時間をかけて、種々の方便を用いて、人々の機根を調熟し、再び法華経を説いて、一仏乗へと導いたのです。
そして、開三顕一の法門が領解できなかった下根の声聞衆に対して、「化城宝処の譬え」をもって、三乗方便一乗真実の法門が説かれます。今回はその「化城宝処の譬え」について、学んでまいります。
化城宝処の譬え
非常に珍しい宝が無量にある場所がありました。そこは五百由旬(約一万キロ)も離れた場所で、途中、山や谷、砂漠など、険しい道を通らなければ辿り着けません。人々のうち、ただ一人の者は、この道をよく知り、しかもたいへん智慧が勝れていたので、彼をリーダーとし、宝の場所をめざして出発しました。
ところが、道があまりに険しいため、人々は途中で疲れ果て、「宝物などもうよい、引き返そう」と言う者も出てきました。そこで、リーダーは「せっかくここまで来たのに帰ろうとするなんて、何てかわいそうな人たちなんだ。ひとつ手段(方便)を講じて、人々を励まそう」と考え、五分の三ほど過ぎたところで、神通力によって、立派な仮の城、つまり化城を設けたのです。そして「もう恐れることも、引き返す必要もありません。この城に入れば、心が安穏となり、元気も回復するでしょう」と告げました。人々は喜んで城に入り、一息ついて安らかになりましたが、さらに「自分はここでよい、もう何も望むことはない」と安住してしまいました。この様子を見たリーダーは、化城を吹き消し、人々に「皆さん、この城は皆さんに一旦休んでもらうために、私が仮に造ったものです。元気を取り戻した今、化城は必要ありません。真の宝処は、もうこの先です。さあ、さらなる元気を出して出発しましょう」と告げました。そして、一同は再び出発し、ついに宝処に辿り着いたのです。
以上の化城宝処の譬えの後、釈尊は「仏も、衆生の心が弱いことを知っている。このため、初めから法華経を説くことをせず、まず仏道へ導く手段・方便として、声聞・縁覚・菩薩の三乗の教えを説いたのである。それは、化城と同じであり、本当の目的ではない。真実の目的とは、一仏乗であり、それは法華経によって成就されるのである」と説かれました。
以上が、化城宝処の譬えについての内容です。
種熟脱の法門について
法華経には、種熟脱が説かれます。種とは、仏様が成仏のもととなる妙法を、人々の心に植え付けることです。熟とは、その種から芽を出させ、肥料をやって順々に育てていくこと、そして脱とは、育て上がった木が、最終的に実を結び、それを収穫することで、これを成仏に譬えるのです。したがって、種熟脱とは化導の始終といって、仏様が衆生を仏の境界に導くすべての課程を括ったもので、仏と人々との関係から仏道成就の因縁を明かしたものなのです。この『化城喩品』では、釈尊と釈尊在世の衆生との仏道の因縁が示されました。つまり、釈尊在世の衆生は、三千塵点劫もの昔に、第十六王子・釈尊の法華覆講によって妙法の種を植えられ、以来生まれるごとに釈尊のもとで仏道修行をし、ようやく法華経を聞くだけの機根に仕立て上げられた。そして、今、ここに法華経の悟りに入ることができる、と明かされたのです。
ここで大切なことは、迹門の『化城喩品』では釈尊自身の本地身を示されていないので、あくまでも衆生の機根を中心とした種熟脱の三益であり、真の種熟脱は釈尊の本地を示された本門に存することを知らなければなりません。
大聖人様は『開目抄』に、
「迹門方便品は一念三千・二乗作仏を説いて爾前二種の失一つを脱れたり。しかりといえどもいまだ発迹顕本せざれば、まことの一念三千もあらわれず、二乗作仏も定まらず。水中の月を見るがごとし。根なし草の波の上に浮かべるににたり」(御書 五三六㌻)
と仰せられているように、本門の成道が明かされなければ、迹門で説くところの教説は有名無実となるのです。
では本門の種熟脱とは、『観心本尊抄』に、
「久種を以て下種と為し、大通・前四味・迹門を熟と為して、本門に至って等妙に登らしむ」(同 六五六㌻)
と、『寿量品』において久遠五百塵点劫の下種を明かし、三千塵点劫及び四十余年の爾前経と法華迹門を熟益とし、『寿量品』に依って得脱したことを脱益というのです。
したがって、久遠の過去に下種を受けた本已有善の衆生は、法華経本門の種熟脱の化導を経て真の成仏を遂げるのです。
末法の衆生は、未だ下種を受けず、善根を積んでいない本未有善の衆生であり、釈尊の熟益・脱益の法では救われません。
故に末法は、久遠元初と同様、久遠の本仏によって、新たに衆生の心田に仏種を下されるべき時です。
『観心本尊抄』に、
「在世の本門と末法の初めは一同に純円なり。但し彼は脱、此は種なり。彼は一品二半、此は但題目の五字なり」(同)
と仰せのように、末法下種の本法とは、御本仏日蓮大聖人の御当体である南無妙法蓮華経の大漫荼羅本尊であり、末法の衆生はこの御本尊を信受し、題目を唱えるところ、即身成仏の境界を得ることができるのです。これが末法における真の種熟脱の三益なのです。
化城即宝処
大聖人様は『御義口伝』に、
「化城の化とは色法、城とは心法を表わしており、爾前権教においては、この色心の二法を無常と説き、法華経においては、常住と説きます。そして、化城とは九界、宝処とは仏界と説かれ、末法においては、御本尊を受持し、南無妙法蓮華経と唱えていくところ、私たち凡夫の色心が本有常住の妙法の当体と開かれ、即身成仏することを化城即宝処というのである(趣意)」(同 一七四五㌻)
とされています。
私たちは、五百由旬の険難悪道を経なくとも、直ちに宝処に至ることができる大聖人様の南無妙法蓮華経を受持信行させていただける喜びを再認識し、さらには多くの人びとを宝処に導いたリーダーのように、自行化他の信心に住し、御命題達成をめざしてさらなる精進をしてまいりましょう。
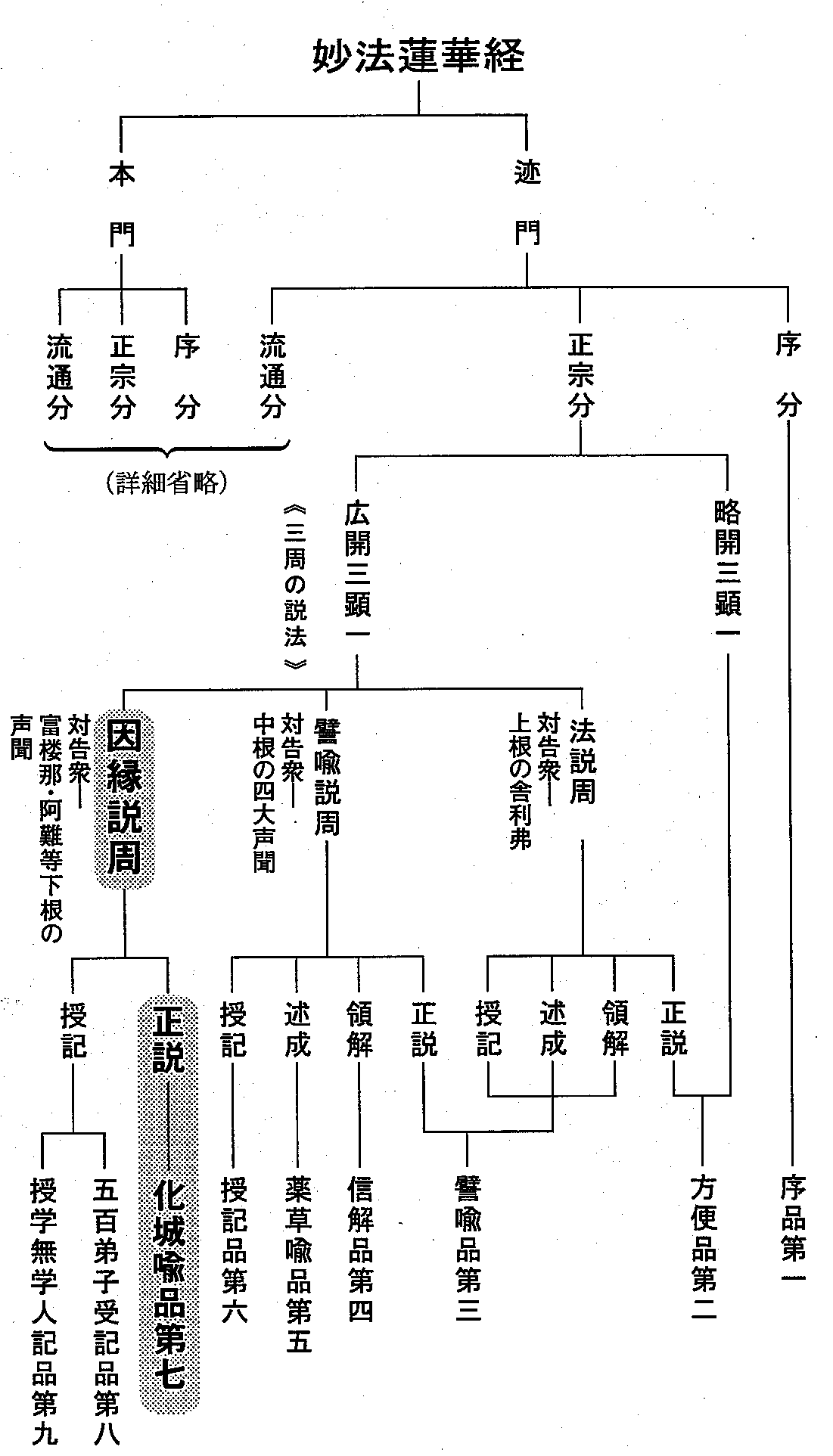
|
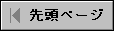
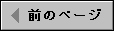
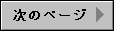
|
| 『基本を学ぼう』目次へ戻る |